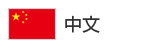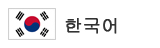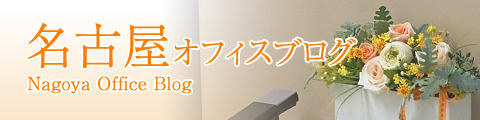知財トピックス
特許出願の目的を明確にする
2017.02.23

特許の存在感を出すためには、特許出願の際にその出願目的を明確にすることが大切です。特許出願された発明の将来の価値は予測できない面もあることは事実ですが、その発明に担わせようとする役割が曖昧であることは、将来、特許の不良資産化を招く一因となる可能性があります。 ここで、特許出願の目的には、様々な分類方法があると思いますが、例を挙げると以下の通りです。
A)実際に実施している製品や製法を保護する目的。
*製品の売上等からさらにランク分けしてもよい。
例)AX中核製品、AY非中核製品
*このカテゴリーの発明は、原則他社へのライセンスアウトはしません。
*AXランクに該当する発明は、出願計画を立てて改良発明を確実に
継続出願を行い、中核製品の特許切れを防ぎます。
B)将来実施する可能性のある製品や製法を保護する目的。
*このカテゴリーに属する発明については、審査請求や中間段階
で、実施計画を都度検証して特許化の必要性を検討します。
*特許成立後に実施可能性が完全に消滅した場合は、適時、
権利放棄、ライセンスアウト、ランクCへの格下げを行います。
C)他社の権利化を阻止する目的。
*自社の自由な研究開発を確保することに特化する防衛出願です。
*原則、審査請求をせずに出願公開を行うのみとします。
D)その他の理由で出願を要する場合。
*理由としては、例えば、産学連携などの共同研究、ビジネス上の
必要性、他社へのライセンスなどです。
また、出願を終えた発明を管理する場合は、実際に契約の対象になっている発明とそうでない発明を区別しておく必要があります。契約書にも番号を付けて発明とひも付しておくとよいでしょう。
A)実際に実施している製品や製法を保護する目的。
*製品の売上等からさらにランク分けしてもよい。
例)AX中核製品、AY非中核製品
*このカテゴリーの発明は、原則他社へのライセンスアウトはしません。
*AXランクに該当する発明は、出願計画を立てて改良発明を確実に
継続出願を行い、中核製品の特許切れを防ぎます。
B)将来実施する可能性のある製品や製法を保護する目的。
*このカテゴリーに属する発明については、審査請求や中間段階
で、実施計画を都度検証して特許化の必要性を検討します。
*特許成立後に実施可能性が完全に消滅した場合は、適時、
権利放棄、ライセンスアウト、ランクCへの格下げを行います。
C)他社の権利化を阻止する目的。
*自社の自由な研究開発を確保することに特化する防衛出願です。
*原則、審査請求をせずに出願公開を行うのみとします。
D)その他の理由で出願を要する場合。
*理由としては、例えば、産学連携などの共同研究、ビジネス上の
必要性、他社へのライセンスなどです。
また、出願を終えた発明を管理する場合は、実際に契約の対象になっている発明とそうでない発明を区別しておく必要があります。契約書にも番号を付けて発明とひも付しておくとよいでしょう。